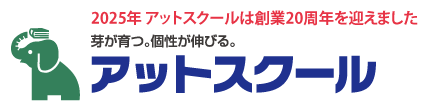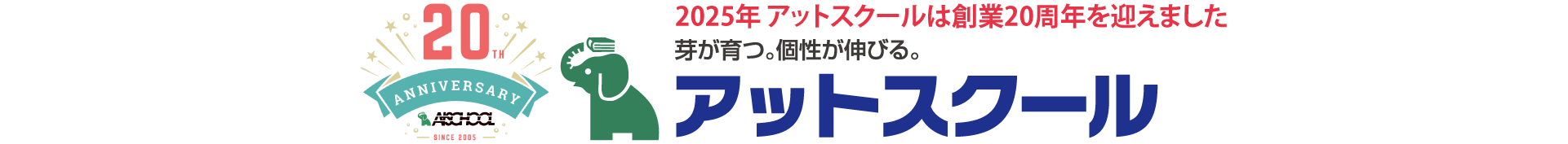AIアドバイス例
このお子様の得意なこと
- 一時的に情報を記憶し、処理する能力が比較的高い
→短い時間で処理する計算や、瞬間的に提示された情報を覚えておくことなどで力を発揮しやすい - 読み書き算数(特に計算面)や、短時間の集中が必要な課題に取り組むときに力を出しやすい
- 自分が得意な分野や興味のあるものに関しては、集中力や意欲が高まりやすい
このお子様の苦手なこと
- 言語による理解力や推理力、思考力、表現力
→ 文章を読んで内容を把握したり、相手にわかりやすく言葉で伝えることに負担を感じやすい - 視覚的情報をもとに推理する課題(イラストや図を見て内容を推測するなど)
- 一時的に複数の情報を同時に保持し、素早く正確に処理する課題(苦手な面もある)
- 視覚情報を素早く正確に処理する課題(複雑な図形や文章を短時間で理解するなど)
※ 上記は「すべてにおいてできない」というわけではなく、あくまで相対的に負担になりやすい領域です。取り組む課題の種類や支援方法によっては、苦手さを補いながら力を発揮できます。
学習面での支援方法
1) 視覚的・具体的な補助の活用
- 文章の説明に絵や図、実物の写真などを添えて理解を助ける
- 行間を広くしたり、1行あたりの文字数を少なくするなど、読みやすいレイアウトを工夫する
- 要点をピクトグラム・シンボルマーク・色分けなどで示し、「重要な情報」がひと目でわかるようにする
2) 音読・読み聞かせ・ICT機器の活用
- 文章を支援者が読み上げ、本人は聞きながら要点をメモ
- 音声読み上げソフトやルビ付き教材を活用
- まず音声や動画で全体像を把握してから文章に取り組む
3) スモールステップによる文章理解練習
- 段落ごとに内容を確認し、キーワードを抜き出す
- 一文ずつ要約やイメージ確認をし、「何を読んだか」を振り返る時間を設ける
- 「この段落には何が書いてあった?」といった質問をこまめに投げかける
行動面・コミュニケーション面での支援
1) 具体的かつ短い指示や声かけ
- 指示は端的に伝え、視覚的にも提示(例:ホワイトボードに書く)
- 情報は一度に多く伝えず、1つずつ確認しながら進める
2)自己肯定感の育成
- 計算や短時間でできる課題で成功体験を積ませ、「やればできる」手応えを感じさせる
- 授業での発言やプリントへの記入ができたときは、すぐにポジティブなフィードバックを
3) コミュニケーション練習
- 自宅や放課後などのリラックスした時間に、簡単な会話のロールプレイ(例:「今日の出来事を一言で伝えよう」)
- 参観日などを活用して、その子の得意なことを周囲に伝え、ポジティブな関係性を築く機会を増やす
学校や家庭での環境設定
1) 担任・支援員・保護者のこまめな情報共有
- 授業での理解度や様子を、連絡帳やICTツールで日々共有
- 宿題や学習の進め方を学校と家庭で連携させる
2) 静かで集中しやすいスペースの確保
- 家庭では、テレビや雑音が少ない部屋を用意
- 学校では仕切りやイヤーマフなどで刺激を軽減する工夫
3) ICT機器や視覚支援ツールの導入
- タブレット・音読ソフト・ルビ付きテキストなどで読みの負担を軽減
- プリントやテストの文字サイズ・フォントへの配慮
まとめ
- このお子様は、一時的な情報処理力や短時間の集中力を活かしつつ、文章理解や言語表現の面では段階的な支援が必要です。
- 特に「文章を読むときに意味をつかむのが難しい」という課題に対しては、ビジュアルや口頭補助、ICT機器の活用、スモールステップでの練習が有効です。
- 保護者や学校が連携しながら「できたこと」に着目し、成功体験を積み重ねることで、自己肯定感と学習意欲が育ちます。
- 1〜2年後に、文章をしっかり理解し、クラスで自分の意見を言えるようになることを目指し、継続的かつ無理のない支援が重要です。
このように、「得意を伸ばし、苦手を補う」視点から、学習・行動・コミュニケーションの各側面を支援し、学校と家庭の両方で環境を整えることで、より自信をもって成長していくことができると考えられます。
ISSPのお問い合わせは、お申込みはこちらから